国枝慎吾の英語勉強法 テニスコート上の最も厳しい先生とは?

※ この記事は、翼の王国2024年10月号に掲載されたものです。
今年1月、私はアメリカ・フロリダ州に拠点を移しました。こちらに来た目的の一つ、それは自分の英語力を磨き直すこと。現在は、全米テニス協会のナショナル・キャンパスで主にジュニアの選手たちを午前中に指導し、午後は近くにある州立大学内の、外国人向けの語学スクールに通うという毎日を送っています。


改めて英語を学び始めて半年以上が経つわけですが……「一筋縄ではいかんなぁ」というのが、正直ないまの感想で、日々“手応え”と“挫折”を味わっています(苦笑)。
こちらに来た当初、私の“なりたい自分”のイメージは、流暢とまではいかなくとも、会話の相手が話す英語をしっかり理解し、自分の伝えたいこともきちんと英語で伝えられる、というもの。その理想の姿を100点とすると、現状は……40点がいいところなんです。

会話の相手が学校の先生であったり、私同様、こちらに移り住んだノンネイティブの人であったり、はたまた、そのようなノンネイティブの人との会話に慣れた相手であれば、ほぼほぼ問題なく、話せるようになったと思います。当初に比べれば英語はスラスラ出てくるようになりましたし、いちいち日本語に変換せずとも、ダイレクトに英語でものを考え語れる場面も増えてきて、自分でも「上達してる!」という実感も。でも……、もっとも厳しい“先生”が、午前中のテニスコートにいるのです。そう、それはジュニアの選手たち。まだ若く、正直で、ノンネイティブとの会話経験も乏しい彼らとの英語でのやりとりが最大の難関で、会話中「ん?」という表情をされてしまうこともしばしば。そのたびに「あ~、まだまだダメなんだ」と、突き落とされるような気分を味わうのです。
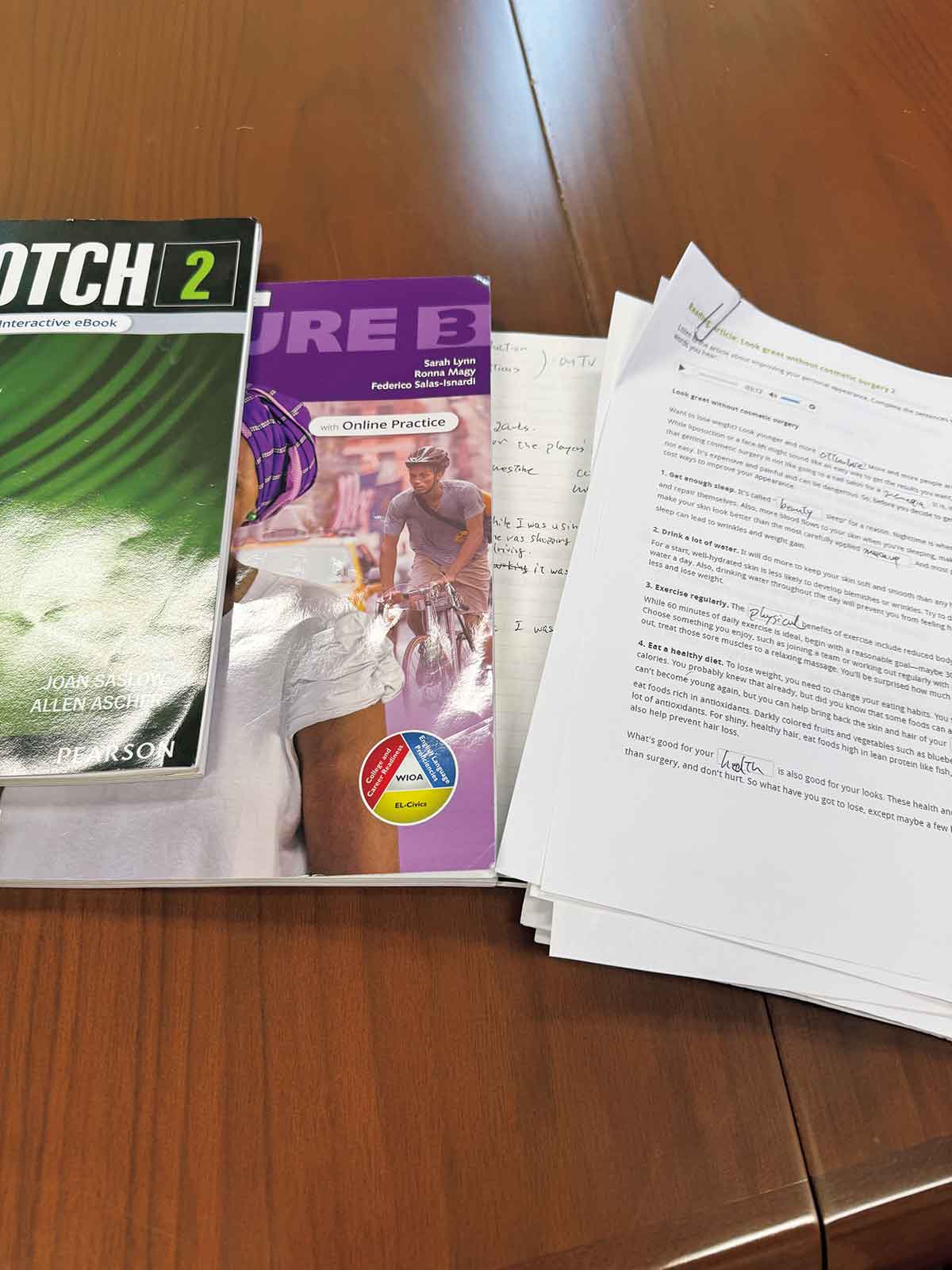
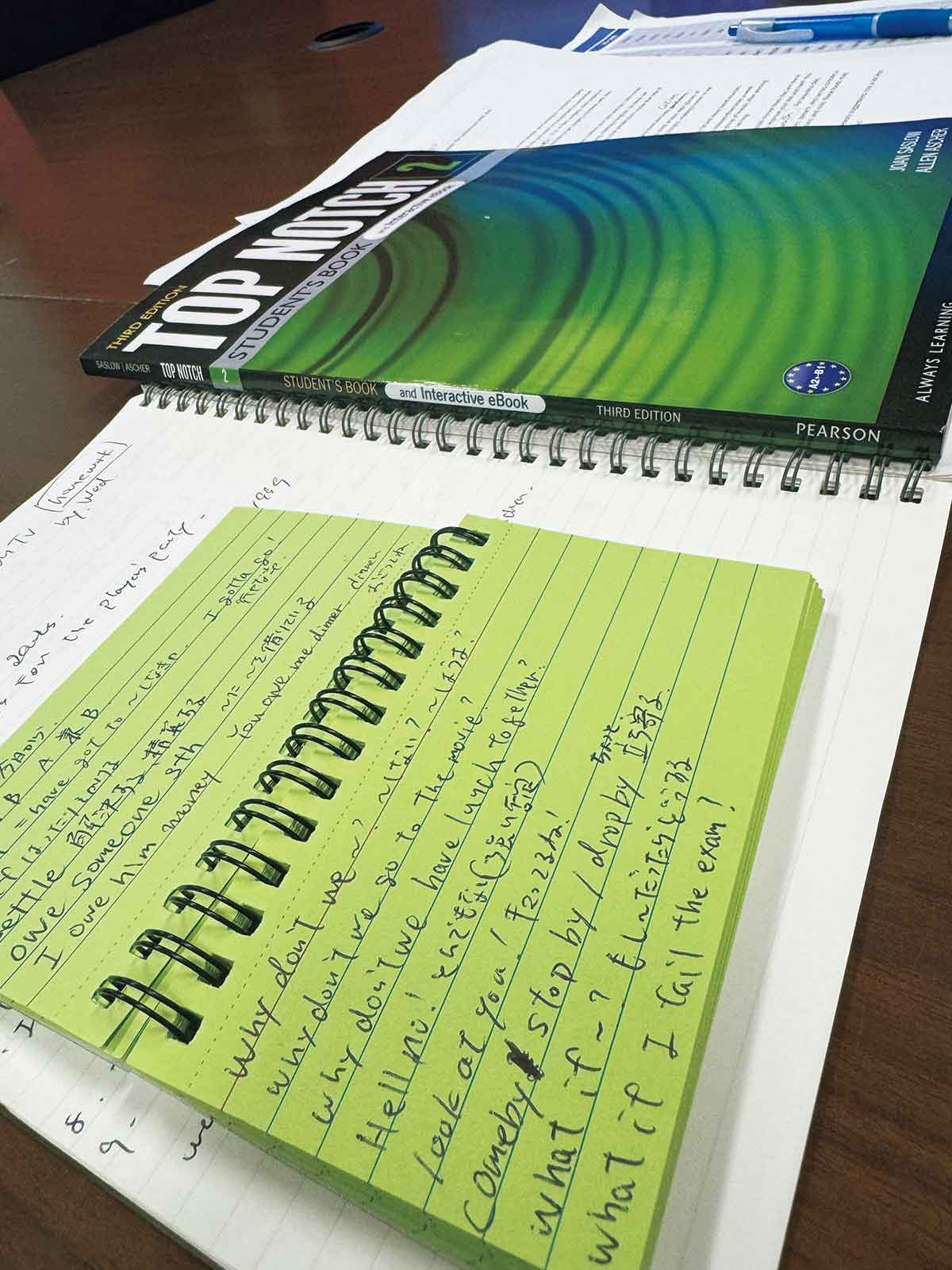
そうそう、英語を学ぶなかで衝撃の事実も判明しました。現役時代、海外遠征の際などに、私は何度も英語のインタビューを受けてきました。その際、数えきれないほど語ってきた「I play tennis」という言葉。しかし、私の発音では「play」ではなく「pray」だと指摘されてしまったのです。いまは、一刻も早く“テニスを祈る”状態から脱したいと切に思い、発音も猛特訓しています。
国枝 慎吾
脊髄腫瘍のため9歳から車いす生活となり、11 歳で車いすテニスと出会う。四大大会とパラリンピックを制覇する「生涯ゴールデンスラム」を達成。23年1 月、世界ランキング1 位のまま引退。
2016年よりスポンサーシップ契約を結んでいるANAは、国枝さんの新しい挑戦を応援し続けます。
